Old Rocks (1962〜1969)
※スクロールバーが隠れている場合は画面上で上下スクロールしてください
ビートルズ登場以降〜1960年代末までに発表されたロック系・ナンバー※Cover Singer (Group) 部分の緑字は持っていない音源
| Title | Original Singer or Group | Cover Singer or Group | Song Writer |
| Out of Time (アウト・オブ・タイム) | The Rolling Stones (1966's Album "Aftermath") | Chris Farlowe (1967's Single) | Mick Jagger / Keith Richards |
ローリング・ストーンズの全曲の中で一番好きな曲です。コーラスのバックでバシッ!バシッ!と決まるギターの音が耳にこびりついていました。 "I said, baby, baby, baby, you're out of time" ここのbaby, baby, baby, の繰り返し部分も妙に耳に残りますね。 |
|||
| Title | Original Singer or Group | Cover Singer or Group | Song Writer |
| Heart of Stone (ハート・オブ・ストーン) | The Rolling Stones (1964's Single) | Mick Jagger / Keith Richards | |
RS5 (ローリング・ストーンズ) の曲をもうひとつ。ミックの粘っこいヴォーカルの後でブライアン・ジョーンズのギターソロに滑り込んで行く辺りが私的に聴きどころでした。ブライアンはRS5のバンド名、命名者であり初期のリーダー、曲作りの面でミックとキースの才能に負ける悔しさからか薬と女性に溺れて行き、やがて脱退を迫られて脱退、その後麻薬中毒で水死と悲運のミュージシャンでしたが、彼の居た頃の RS5 の曲の方が構成的に好きな曲が多いです。 |
|||
| Title | Original Singer or Group | Cover Singer or Group | Song Writer |
| The Letter (あの娘のレター) | The Box Tops (1967's Single) | Sammi Smith (1979's Single) Amii Stewart (1980's Album) Joe Cocker (1970's Single) & Others |
Wayne Carson Thompson |
`60年代後半の英国バンドではRS5やアニマルズがRソウル色が強かったでしょうが、アメリカでは本場メンフィスで結成された白人グループ The Box Tops (当初はThe Devilles) が一番手でした。プロデュースしたダン・ペンという人はソング・ライターとして有名に成りサザン・ソウル色の強い曲を書く人としてわたしも注目してソロアルバムも全部揃えましたが、「ビートルズが嫌い」という彼の言葉が載った記事を見てから彼の曲は好きでも、ダン本人への興味は失せました。(まぁ、アンチ・ビートルズの人達は多いのかも知れませんが) この曲は全米1位のシングル・ヒットとなり、日本でもそこそこのヒットを記録していました。この時ヴォーカリストのアレックス・チルトンは16歳だったそうです。  |
|||
| Title | Original Singer or Group | Cover Singer or Group | Song Writer |
| Soul Deep | The Box Tops (1967's Single) | Lisa Burns (1978's Album) Clarence Carter (1969's Album) & Others |
Wayne Carson Thompson |
ボックス・トップスの出現により [Blue Eyed Soul] という言葉が定着しました、[青い目をしたソウル・ミュージック] 白人が歌うブラック・ミュージックという意味です。 ボックス・トップスの曲としては "The Letter"はより南部色が強くこちらの方が好きです。どちらもカントリー・シンガーのウェイン・カーソンですのでナッシュビルの匂いはします。確かにアレックス・チルトンのヴォーカルは黒っぽいです。 |
|||
| Original Singer or Group | Cover Singer or Group | Song Writer | |
| These Eys | The Guess Who (1969's Single) | Natalie Cole (1981's Album) & Others |
Randy Bachman, Burton Cummings |
ゲス・フーはカナダで結成されたバンドで、後にB.T.O. (バックマン・ターナー・オーヴァードライヴ) を結成してそちらの方が有名に成ってしまいましたが、ランディ・バックマン達が最初に作ったバンドです。 ゲス・フーは "American Woman"の全米No.1ヒットを放ちますが日本では一発屋タイプのバンドとして見られがちです。ただ、彼らのファースト・アルバム『Wheatfield Soul』からシングル・カットされたこの "These Eyes" も一応BB誌で6位になるヒットをしています。 淡々と流れるタイプなので、日本ではヒットしないと感じて敬遠されたらしく、日本でのシングル盤は見た事ありません。 カナダのバンドながら、サザン・ロック・サウンドを連想させる作りが印象的でやはり若干 [Blue Eyed Soul] を感じます。 |
|||
| Title | Original Singer or Group | Cover Singer or Group | Song Writer |
| Mighty Quinn (Quinn the Eskimo) | Manfred Mann (1968's Single) | Julie London (1969's Album) Bob Dylan (1970's Album) The Hollies (1969's Album) & Others |
Bob Dylan |
マンフレッド・マンは結構その後に名を成すミュージシャンが在籍していた英国のグループでした。シンガーのポール・ジョーンズ、ベーシストのジャック・ブルースやクラウス・フォァマンなど、`64年のデビュー時から他人の曲のカヴァーを割と多く録音していたようです。 ディランの曲もこの曲以前に数曲録音されています。この "Quinn the Eskimo"という曲を "Mighty Quinn" とタイトルを変えて発表したとき、ディラン本人は未発表で先にマンフレッド・マンのヒット曲として広まってしまいました、全英1位、全米10位。 確かに彼らの曲の方がヒット性はある曲調です。 |
|||
| Title | Original Singer or Group | Cover Singer or Group | Song Writer |
| I Am a Rock | Paul Simon (1965's Single) | Simon & Garfunkel (1966's Album & Single) The Hollies (1966's Album) & Others |
Paul Simon |
サイモンとガーファンクル結成前にポール・サイモン名義で一度発表されていた "I Am a Rock"、殆ど注目されることなく、サイモンとガーファンクルとして再録後に、全米3位になるヒットとなりました。ソロで歌ったヴァージョンはフォーク・ソングタイプですが、 S&Gヴァージョンは確かにフォーク・ロックとなっています。バックのギターサウンドがアコースティックからエレクトリックな音に変わっただけで印象が変わるのですね。 大好きな曲です。 |
|||
| Title | Original Singer or Group | Cover Singer or Group | Song Writer |
| A Hazy Shade of Winter (冬の散歩道) | Simon & Garfunkel (1966's Single) | The Bangles (1987's Single) & Others |
Paul Simon |
この曲はS&G・ナンバー中ではかなりロックぽい曲です。アメリカではTOP10に入りませんでしたが、バングルスがカヴァーしたリバイバル・ヒットはBB誌で2位になるヒットとなりました。ただ、好みとしては力強いS&Gヴァージョンの方が好きです。 |
|||
| Title | Original Singer or Group | Cover Singer or Group | Song Writer |
| Born To Be Wild (ワイルドでいこう!) | Steppenwolf (1968's Single & Album "Steppenwolf") | Mars Bonfire (Dennis Edmonton) |
|
タイトルは時代を感じますが、曲自体は古さを感じない上質のロックです。アメリカン・ハード・ロックの原点に思えます。ピーター・フォンダ主演の映画『Easy Rider』に使用されて世界中でヒットしました。ステッペンウルフのメンバーはカナディアン、アメリカン、ジャーマンなどの混合メンバーでカリフォルニアで結成されています。他にもヒット曲が多くダンヒルレコードの稼ぎ頭でした。 `60年代後期のダンヒル(Dunhill)レーベルは絶好調で、The Grass Roots、Three Dog Night、Mamas & Papas、Hamilton, Joe Frank & Reynoldsなど全米チャートのTOP10内ヒットを連発していました。 |
|||
| Title | Original Singer or Group | Cover Singer or Group | Song Writer |
| From a Distance (孤独の世界) | P. F. Sloan (1966's Single & Album "Twelve More Times") | Phil 'Flip' Sloan | |
バリー・マクガイアが`65年に全米No.1ヒットを放った "Eye of Destruction 邦題:明日なき世界" の作者がP..F.スローン。 彼はスティーヴ・ヴァリと組んでソング・ライターとしてジョニー・リヴァース、ママス&パパスやハーマンズ・ハーミッツ等のヒット曲を作ったことでそこそこ知れ渡っていましたが、シンガーとしての認知度はかなり低かったようです。 この曲はアメリカで`66年にシングル発表もBB誌チャート109位とほぼ不発。日本では同年に日本ビクターからシングル発表、小ヒット。その後Dunhilllレーベル移籍に伴い東芝音楽工業から再発シングル化。当時東芝はダンヒルに力を注いでいたこともありプッシュされて`60年代終盤の大ヒット曲となっています。ディラン、S&G、などが牽引したフォーク・ロックの名曲の一つです。 |
|||
| Title | Original Singer or Group | Cover Singer or Group | Song Writer |
| Here's Where You Belong | P. F. Sloan (1966's Album "Twelve More Times") | Phil 'Flip' Sloan | |
同じく1966年発表のP.F. スローンの曲。この曲も‘60年代フォーク・ロックの名曲のひとつでしょう。シングル化はされていませんが、この時期のディランやS&Gが好きな人なら必ずやハマルでしょう。 |
|||
| Title | Original Singer or Group | Cover Singer or Group | Song Writer |
| Somebody to Love (あなただけを) | The Great Society (recorded 1966, 1968's Album) | Jefferson Airplane (1967's Single) | Darby Slick |
ジェファーソン・エアプレインで有名になったグレース・スリックが最初に組んでいたバンド、グレート・ソサエティ時代からのレパートリーで [サイケデリック・ロック] と呼ばれていた時代を代表する曲であり、グレースを有名にした曲です。作者のダービー・スリックはグレース・スリックの弟でグレート・ソサエティでのギターリスト(ジェファーソン・エアプレインには参加せず)。 |
|||
| Title | Original Singer or Group | Cover Singer or Group | Song Writer |
| 96 Tears (96粒の涙) | ? and the Mysterians (1966's Single) | Garland Jeffreys (1981's Album) Aretha Franklin (1967's Album) & Others |
Rudy Martinez |
?アンド・ザ・ミステリアンズはミシガン州出身のガレージ・ロック・バンドのひとつでこのあまりにもシンプルなオルガンの音が妙にクセになり催眠術にかかったような世界を感じてしまいます。ガレージ・ロックと言えば後にパンク・ロックと呼ばれるように成るなどスリー・コード中心のシンプルで荒っぽいロックの様なイメージですが、この酔わされる様な感覚は西海岸の [サイケデリック・ロック] に近い感覚です。 全米中が酔わされてBB誌、CashBox誌のチャートで共に1位、カナダや日本でもヒットしました。 |
|||
| Title | Original Singer or Group | Cover Singer or Group | Song Writer |
| (We Ain't Got) Nothing' Yet (恋する青春) | Blues Magoos (1966's Single & Album "Psychedelic Lollipop") | Ron Gilbert, Ralph Scala, Mike Esposito | |
このバンドBlues Magoosもニューヨーク州で結成されたガレージ・ロック・バンドのひとつで、"Nothing' Yet" は [ドン・ドコドコドコ・ドコドコ] と繰り返される御呪いのようなリズムが癖になる奇妙な曲ながら全米5位にまで登るヒット成りました。収録アルバムのタイトルが『Psychedelic Lollipop』とサイケデリックを意識していたようです。 |
|||
| Title | Original Singer or Group | Cover Singer or Group | Song Writer |
| Words (恋の合言葉) | The Monkees (1967's Single & Album "Pisces, Aquarius") | Tommy Boyce, Bobby Hart | |
モンキーズの楽曲はソング・ライーター・チームも厳選されていて良質のポップ系ロックが沢山ありますが、この曲はかなりロック色が強い一曲。作曲家チームとしても自らもヒットを出しているボイス&ハートが作った曲です。アレンジが計算されているのが判るほどによくできた曲です。 |
|||
| Title | Original Singer or Group | Cover Singer or Group | Song Writer |
| Lodi | Creedence Clearwater Revival (1969's Album "Green River" &
B-side of Single "Bad Moon Rising" ) |
Tom Jones (1970's Album) Emmylou Harris (1992's Album) Smokie (2002's Album) & Others |
John Fogerty |
クリーデンス・クリアウォーター・リバイバル (CCR) は`60年代デビュー組で最もアメリカン・ロックを感じるバンドだと思います。カリフォルニア出身ながらナッシュヴィルの匂い、更にはもう少し南部のサザーン・ロック、スワンプ・ロックの香りさえもします。シンプルなロックのリズムの乗せてジョン・フォガティの生み出すメロディーが気持ちよいバンドでした。BB誌のチャート2位曲が5曲、3位曲と4位曲が各一曲と連続でヒットシングルを出していましたが何故か1位ヒットは出せませんでした。その中で、B面扱いで52位までしか上がらなかったこの曲がわたしは一番好きです。ところで「Lodi」とはカリフォルニア州のある都市の名前であっているのでしょうか? |
|||
| Title | Original Singer or Group | Cover Singer or Group | Song Writer |
| Down On The Corner | Creedence Clearwater Revival (1969's Album "Willy and the Poor Boys" & B-side of Single "Fortunate Son") | John Fogerty | |
続いてもCCRでこの曲がわたしがCCRを聴くきっかけになった曲です、"Down on the Corner" 。全作アルバムがアルバムチャートで1位に成って作られた4作目のアルバムからのシングル曲でこちらも最初はB面として発売され、こちらの方がヒット(チャート3位)したのでその後は両A面扱いに成っています。この曲もシンプルなロック・リズムに乗せたカントリーっぽい曲調です。  |
|||
| Title | Original Singer or Group | Cover Singer or Group | Song Writer |
| Killing Floor | Howlin' Wolf (1964's Single & 1965's Album "The Real Folk Blues") | The Electric Flag (1968's Album) Led Zeppelin (1969's Album) Jimi Hendrix (1984's Album) & More |
Chester Burnett |
シカゴ・ブルースマンでブルース・ハープ奏者のハウリン・ウルフのオリジナル曲(Chester Arthur Burnettが彼の本名)。早くからロック・ミュージシャンから憧れを抱かれていた人らしくロックに近い曲調が多く、専属ギターリスト Hubert Sumlin のギターもキレがあり、多くのロック・ミュージシャンに彼の曲は取り上げられていました。 わたしがこの曲を最初に聴いたのは白人ブルース・ロック・ギターリスト、マイク・ブルームフィールドが作ったエレクトリック・フラッグのアルバムでした。まさに「かっこ好いロック」という言葉がぴったりでした。 今でもエレクトリック・フラッグの方のヴァージョンが好きです。 後にレッド・ゼップが "The Lemon Song" としてこの曲をベースにした曲を録音していますが、当初作者クレジットがメンバー4人のみだった為にクレームが付き最近のクレジット欄には Chester Burnett が追加されています。 |
|||
| Title | Original Singer or Group | Cover Singer or Group | Song Writer |
| Inside-Looking Out(孤独の叫び) | The Animals (1966's Single & 1966's US Album "Animalization") | Grand Funk Railroad (1969's Single & Album) The Mops (1968's Album) & More |
John Lomax, Alan Lomax, Eric Burdon, Chas Chandler |
エリック・バードンをヴォーカルにイギリスで`63年に結成、`64年にデビューしたアニマルズ。「朝日のあたる家」「悲しき願い」「朝日のない街」と立て続けにUK・TOP3以内(米BBチャートでは15位以内)のヒットを放ち、特に「朝日のあたる家」は全英・全米共に1位、他全世界でヒットしていました。ただ、どれもが他人の作品でしたが、この "Inside-Looking Out(邦題:孤独の叫び" はオリジナル・ソングで反対に他のミュージシャンにカヴァーされています。アニマルズはデビュー前の`63年にはソニー・ボーイ・ウィリアムソンのバックを務めた事も有り元々はブルース系のロックをしていましたが、この "Inside-Lokking Out" の収録アルバム発表後、アメリカにわたりメンバーも少し入替て「Eric Burdon & The Animals」とバンド名も変えてサイケデリック・ロック・バンドにサウンド変化してしまいました。曲の出来としてはグランド・ファンク・レイルロードの方がロックらしいのですが間奏が長く全体で9分半ほどあります。日本のモップスヴァージョンは鈴木ヒロミツさんはバードンのファンなのでアニマルズ風の演奏・ヴォーカルで迫っていて充分なカヴァー・ヴァージョンに成っています。 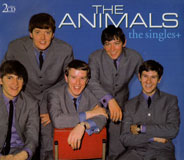 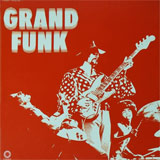 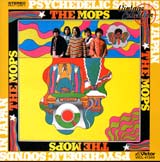 |
|||
| Title | Original Singer or Group | Cover Singer or Group | Song Writer |
| Elegy | Colosseum (1969's Album "Valentyne Suite") | James Litherland | |
ジョン・メイオール&ザ・ブルースブレイカーズに一時的に在籍していたドラマー、ジョン・ハインズマンが主に成って結成されたイギリスのバンドで、最初はブルース・ロックをベースにしていたバンドでしたが、ホーン楽器サックスを巧みに取り入れたジャズやファンク的な多彩なジャンルを組み合わせたバンドへと変化して行きました。 曲主体に聴くバンドと云うより、クラプトンのクリームの様な [演奏を聴く] といったタイプのバンドでした。 `70年に解散しましたが、20数年後に再結成されています。 この曲はセカンドアルバムでイギリスでのアルバム・チャート15位(ファーストも同順位のヒット)になり邦盤も出されて『ヴァレンタイン組曲』というタイトルが付けられました。発売の数年後に初めて聴き、驚きました。とても`60年代に作られたアルバムだとは思えないほど構成や演奏が凄くこの第一期のコロシアムを聴きこんでいました(スタジオ盤4作、ライヴ盤1枚)どれも良いです。。1995年にライブで再結成して1997年にスタジオ盤も出たらしいですが、メンバーがかなり変わっているようで未聴です。 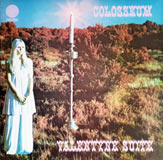 |
|||
| Title | Original Singer or Group | Cover Singer or Group | Song Writer |
| Gimme Some Lovin' (愛しておくれ) | The Spencer Davis Group (1966's Single) | Olivia Newton-John (1978's Album) The Blues Brothers (1980's Album) & Others |
Steve Winwood, Spencer Davis, Muff Winwood |
スペンサー・デイヴィス・グループは`65年に結成されたイギリスのロックバンド。ブルースを演奏するバンドが多かった時代に初期からR&B系の黒人シンガーのカヴァーなどをしていました。デビュー時の演奏を聴くと演奏技術は如何にもデビューし立てのバンドといった感じでしたがウィンウッドのヴォーカルは抜けていました。この曲はそのウィンウッドが中心に成って作られたオリジナルで彼らの代表作。R&B色の強いロックですが時を経ても色あせていない名演です。カヴァーもかなりされています。 |
|||
| Title | Original Singer or Group | Cover Singer or Group | Song Writer |
| I'm a Man | The Spencer Davis Group (1967's Single) | Chicago (1969's Album) & Others |
Steve Winwood, Jimmy Millar |
もう一曲、SDGの代表曲。ヤードバーズの同名異曲が`60'sロックファンには有名ですが、この曲も劣らない名曲です。`70年代HRシーンをを予想するようなハードな演奏にスティーヴ・ウィンウッドのヴォーカルが素晴らしいです。やはり残すべき演奏でしょう。 |
|||
| Title | Original Singer or Group | Cover Singer or Group | Song Writer |
| Time of the Seasons (ふたりのシーズン) | The Zombies (1968's Album "Odessey and Oracle" & Single) | Rod Agent | |
後の`72年に "Hold Your Head Up" 等のヒット曲を放つ Agent のリーダー、ロッド・アージェントが中心に成って結成され`64年にデビューしたイギリスのロック・バンド、ゾンビーズ。"She's Not There" を全米No.1になるヒットで華々しく脚光を浴びましたが、`66年、`67年と不発に終わり`68年この曲の入ったアルバム『Odessey and Oracle』製作後に仲違いで解散してしまいました(その後20数年後に再結成)。解散後にこの曲がアメリカでシングル化されて再びBB誌TOP100チャートのNo.1ヒット。前回の#1曲同様、アメリカン・ロックではまず生まれないような不思議な魅力を持った曲で一度聴いたら忘れられない曲に成っています。ゾンビーズは他の曲にも良い曲がかなりあります。 "I Love You" という`65年に発売されたシングルB面曲を日本のGSバンド、カーナ・ビーツが "好きさ好きさ好きさ" と変えて発表した日本語ヴァージョンが我が国で大ヒット、`68年にアメリカで再発までされました(ヒットしなかった様ですが)。 |
|||
| Title | Original Singer or Group | Cover Singer or Group | Song Writer |
| Light My Fire (ハートに火をつけて) | The Doors (1967's Album "The Doors" & Single (recuted)) | Amii Stewart (1979's Single) José Feliciano (1968's Single & Album) & Others |
Robby Krieger, Ray Manzarek, Jim Morrison, John Densmore |
ドアーズのデビュー・アルバム収録曲。`60年代後半に米西海岸中心に広がったサイケデリック・ロックと呼ばれるジャンルの中での代表曲。アルバム・ヴァージョンは7分程の長さでしたがシングル化の際2分50秒程に短縮されてしまいました(サイケデリック要素を味わう間奏部分がカット)。 シングル盤は "Happy Together" 同様、全米ビルボード誌、キャッシュボックス誌共にチャート1位になるヒットでした。リーダーでヴォーカリストは薬で若くして亡くなりましたが、同年代(27歳)に同様な死を遂げたジャニス・ジョプリン、ジミ・ヘンドリックス、ブライアン・ジョーンズと共に [27 Club Members] と呼ばれる様に成っています。 |
|||
| Title | Original Singer or Group | Cover Singer or Group | Song Writer |
| The Game of Love | Wayne Fontana and The Mindbenders (1965's Single & Album "The Game of Love") | Sylvie Vartan (1966's Album) Tex Pistol (1987's Single & Album) |
Clint Ballard Jr. |
ウェイン・フォンタナ&ザ・マインドベンダーズはイギリスのマンチェスターで1963年に結成されたビート・バンド。この "ゲーム・オブ・ラブ" は6枚目のシングルで`65年にアメリカのヒット・チャートで1位、イギリスで2位の大ヒットと成っています。導入部(イントロ部分)が実に印象的なロックですが、全体的には古いタイプの曲です。ただ、何故か時々口ずさんでいたような曲でした。この曲のヒットの後、結成者のウェイン・フォンタナは脱退してソロ・シンガーに。残ったバンドはマインド・ベンダースとして引き続きヒットを出しますが、フォンタナは忘れ去られていきました。 |
|||
| Title | Original Singer or Group | Cover Singer or Group | Song Writer |
| Jydy in Disuguise (With Glasses) (ジュディー-のごまかし) | John Fred & His Playboy Band (1967's Single & Album "Agnes English") | John Fred Gourrier Andrew Bernard |
|
1967年10月に発売されて徐々にポップ・チャートを上がり、遂にビートルズの "Hello Good bye" を抜いて翌年1月に全米1位に成った有名曲。ジョン・フレッドやプレイボーイ・バンドという名は知られていませんが、この曲だけは時代が流れても時々耳にします。歌ナシのメロだけで流れていた事も有りました。結構覚えやすいバブルガム・ミュージック的な作りです。 |
|||
| Title | Original Singer or Group | Cover Singer or Group | Song Writer |
| Games People Play (孤独の影) | Joe South (1968's Single & Album "Introspect") | Dolly Parton (1969's Album) Inner Circle (1994's Single) & Others |
Joe South |
ジョー・サウスも日本では名前を殆ど知られていない人。ただ、この曲もそうですが、彼が作った曲を多くのシンガーがレコーディングしていて、SSW、スタジオ・ミュージシャンとして`50年代から活動していたとの事です。 その彼が最初に自身の歌で出したヒット曲がこの "Games People Play" 、邦題の「孤独の影」と踊るような「曲調」がどうもマッチしないのですが、レゲエ・グループのインナー・サークルがカヴァーしたレゲエ調を聴くと、「陽気に過ごすことが、孤独な人生のゲームを上手くプレイできること」とたしなめられているような気もします。 時々、思い出すメロディーです。このジョー・サウスの作った曲で一番売れたのはリン・アンダーソンの "Rose Garden"。 |
|||
| Title | Original Singer or Group | Cover Singer or Group | Song Writer |
| I Need Love | Dave Clark Five (1965's US Album "I Like It Like That" & 1967's UK Single) | Dave Clark, Mike Smith | |
`50年代後半にロンドンで結成されたビートルズ等と同世代のビート・バンド、デイヴ・クラーク・ファイヴ。1964〜68年頃が人気の有った時期でしょうが、こと`64〜`65年にだけ関しては本国よりもアメリカでの人気の方が凄かったバンドです。リーダーのデイヴ・クラークはドラマーで軽快なドラムスを前に押し出したビートルズ系のロックタイプが主でしたが、この曲はかなり黒っぽく当時で云えばローリング・ストーンズやフーのサウンドに近いと思います。アメリカで先にアルバム収録で発売後にイギリスでのみ "Nineteen Days" のB面扱いでシングル化されていました。イギリスでのみシングル化というのがこの曲の曲調を表しています。以降ヒット曲は本国のみに成っていきました。 このデイヴ・クラーク・ファイヴはビート・グループ・バンドに珍しくサックス・プレイヤー(デニス・ペイトン)がメンバーに居ました。 |
|||
| Title | Original Singer or Group | Cover Singer or Group | Song Writer |
| I Woke Up This Morning | Ten Years After (1969's Album "Ssssh.") | Alvin Lee | |
`60年代ロック・シーンにおいて最も速弾きの名手として知られていたのがアルヴィン・リー、そのアルヴィン・リーが18歳頃からバンド活動を開始して`66年にはTen Years Afterという名前のブルース・ロックバンドでステージに上がっていたとの事です。`67年にレコード・デビュー、これは既に4作目となるアルバムからの曲に成ります。 彼のオリジナル曲なのですが、ブルース色強くサウンドはヘビーで、この時代のブルース・ロック系の中でもかなり聴き応えのある演奏に成っています。ウッドストック・フェスで人気を博したバンドらしく演奏力で聴かせるバンドでした。 |
|||
| Title | Original Singer or Group | Cover Singer or Group | Song Writer |
| These Boots Are Made for Walkin' (にくい貴方) | Nancy Sinatra (1965's Single & Album "Boots") | Lee Hazlewood (1966's Album) |
Lee Hazlewood |
フランク・シナトラの娘さん、ナンシー・シナトラ。このシングルは彼女の14枚目のシングル。それまでは前作 "So Long Babe" が本国アメリカで漸く86位のヒットと成る程度でしたが、初期の曲は御大の娘さんという認知度も有り日本やイタリアではヒットしていたので、曲調の問題だったのでしょう。そしてこの男っぽくロック調の曲で歌われた曲は本国だけでなくイギリスを始めヨーロッパ各国で大ヒットしました。日本でも少女から変身、大人びたナンシーという事でかなりヒットしました。作者は後にデュエットアルバムなどを一緒に作るリー・ヘイゼルウッドでその後もナンシーに曲を多く提供しています。 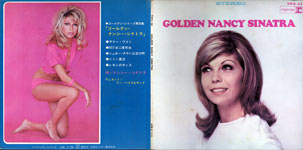 |
|||
| Title | Original Singer or Group | Cover Singer or Group | Song Writer |
| Happy Together | The Turtlles (1967's Album "Happy Together" & Single) | Kimiko Kasai (1975's Album) T.G. Sheppard (1978's Single) & Others |
Alan Gordon, Garry Bonner |
`60年代後半、ボブ・デイラン・ソングのカヴァーをする幾つものロック・バンドが居ました。バーズやマンフレッド・マン等が有名ですが、タートルズも "It Ain't Me Babe 邦題:悲しきベイブ" でデビユーしていました。この曲 "Happy Together" はもともと彼らが吹き込む予定で作られた訳ではなかったらしく、他のシンガーが見つからずに回ってきた曲だという事です。作者のアラン・ゴードンはスリードッグ・ナイトやレスリー・ゴーアなどにも曲を提供している中堅ライターでした。 スロー〜ミディアム・テンポのロック・ナンバーで徐々に盛り上げって行くコーラスも魅力的でビルボード誌でもキッシュボックス誌でもナンバー・ワンになるヒット曲と成りました。声質が特徴あるリード・ヴォーカルはハワード・カイランという人。後にフランク・ザッパの The Mothers of Invention に加入したりソロに成ったりした後、タートルズ再結成に戻ったりしましたがタートルズ自体はヒットと縁遠く成っています グループ名がコメディアンの様な名前でしたので、ロック、ポップス系のバンドだと思えなかったのが最初の印象でしたが、この曲のヴォーカルにハマりました。ヴォーカリストはハワード・カイラン、枯れた声という程ではないのですが、どこか魅力的な声です。囁くようにも聞こえます。‘67年にビルボード誌、キャッシュボックス誌共にチャート1位になるヒットです。トップ10以内のヒット曲は他にも4曲ほどありますが、1位はこの曲だけでした。ほかの曲はポップス系の曲です(ディランの曲もポップスアレンジ)。  |
|||
| Title | Original Singer or Group | Cover Singer or Group | Song Writer |
| Roosevelt And Ira Lee (Night Of The Mossacin) (ルーズヴェルトとアイラ・リー) | Tony Joe White (1969's Album "...Continued" & Singles) |
Tony Joe White | |
トニー・ジョー・ホワイトのセカンド・アルバムからの一曲で、エルヴィス・プレスリーによって有名になった彼の作品 "Palk Salad Annie" とかなり似た曲ですが、こちらの "Roosevelt And Ira Lee" の方がよりロック色が強い曲です。ギターの使い方が「ジミ・ヘンドリックスが生きていた時代なのだ」とふと思わせる音使いです。(勿論ジミ・ヘンは参加していませんが) |
|||
| Title | Original Singer or Group | Cover Singer or Group | Song Writer |
| My Reservation's Been Confirmed (予約はOK) | Herman's Hermits (1966's Single) | The Doughboys (2019's Album) | Charles Silverman, Derek Leckenby, Keith Hopwood |
ポップス主体のアイドル系のバンドで多くのヒット曲を持つハーマンズ・ハーミッツ。ただ意外にもシングルB面にロック系の曲が隠されています。"Got a Feeling" やこの曲 "My Reservation's Been Confirmed" など。この曲のA面は "Dandy" 。ヒット曲の多くはプロのソング・ライター依頼曲でしたが、この曲はメンバーのデレクとキースにチャールス・シヴァーマンという作詞家さんの共作。メンバーは売れ線でなくともロック系を演奏したかったと伺われます。 近年アメリカのダグボーイズというバンドがこの曲をカヴァーしているのを偶然見つけました。"96粒の涙" などオールド・ロックのカヴァーばかりしているアルバム内です。カナダにも同名のダグボーイズが居ましたが、アメリカンバンドの方です。 |
|||
| Title | Original Singer or Group | Cover Singer or Group | Song Writer |
| Our Love Is Drifting | The Paul Butterfield Blues Band (1965's Album "The Paul Butterfield Blues Band" ) | Paul Butterfield, Elvin Bishop | |
`60年代後半のブルース・ロックを聴き漁っているとポール・バターフィールドにたどり着きます。イギリスでE・クラプトンやピーター・グリーンがブルースをロック手法で演奏し始める前にポール・バターフィールドは本国アメリカで演奏していました。デビュー・アルバムに成るこのアルバム、殆どの曲がオリジナルは既存のブルース・ナンバーですがこの曲はオリジナルです。オリジナルと云っても他の曲と並べるとやはりカヴァー曲のロック風アレンジと思えて仕舞えるほど、オリジナリティは薄い感じですが1965年という年代を思うと凄いです。 ギターはマイク・ブルームフィールド、バンドの演奏も凄く次作の『East-West』共々、ブルース・ロック史に残る名演だと思います。ウッドストック・フェスなどで人気を博したのも納得です。 |
|||
| Title | Original Singer or Group | Cover Singer or Group | Song Writer |
| My Days Are Numbered | Blood, Sweat & Tears (1968's Album "Child Is Father to the Man" ) | Al Kooper | |
アル・クーパーという多彩なミュージシャンは`60年代〜`70年代のアメリカのロックシーンにおいて一線ではなく表から若干退いた裏方的な位置で大活躍した人で好きなミュージシャンのひとりです。ディランやジミヘンのアルバムにも参加していましたし、わたしのページでも取り上げているジョージ・ハリスンやベティ・ライトのアルバムでも名を見ること出来ます。1969年から21世紀に入ってもソロ・アルバムを出していますが、この曲はソロ活動を始める前、ブラッド・スェット・アンド・ティアーズを結成して発売したバンドのデビュー作 からの一曲。結成しておきながらメンバーと目指す音楽性の違いから直ぐに自らバンドを抜けています。 曲は`60年代後期のロックが新時代を迎えることを予感できる様な仕上がりです。ただアルバム自体は実験的な要素が多く、チャート50位前後で低めの注目度だった様です。反面アルが抜けたバンドはセカンド・アルバムで [ブラス・ロック] というジャンルで認識され成功を収めています。 |
|||
| Title | Original Singer or Group | Cover Singer or Group | Song Writer |
| I Stand Alone | Al Koper (1969's Album "A Stand Alone") | Al Kooper | |
ブラッド・スェット・アンド・ティアーズを抜けたあと、マイク・ブルームフィールドなどと一緒にセッションを行い、その模様をレコード化するといった「セッション・ライヴ、スーパーセッション」形式の先駆け作品を作りましたが、初めてのソロ・アルバムを発表。そしてこの曲がアルバムのタイトル曲に成ります。 はなからシングル化をするような意図がなく「ひとりで旅立つ」と思えるようなコンセプトの下で作られいると思えます。自由の女神の顔を自身に挿げ替えたデザインからも感じられるようにアメリカン・ミュージックの種々な要素が散りばめられています。(私的には "Bluemoon of Kentucky" の選曲が意外で嬉しい) タイトル・ナンバーであるこの曲、寂しげに感じる歌詞ながら前を向いて進むメッセージ・ソングでサウンド的には如何にも`69年らしいというか、ロック・リズムを持たないプログレ系サウンド。今聴くとノスタルジーを感じる部分も有りますが、忘れえない歌唱です。 |
|||
| Title | Original Singer or Group | Cover Singer or Group | Song Writer |
| Free Me | Paul Jones (1967's Siingle and Album ) | Mark London / Mike Leander | |
ブルティッシュ・ビート・バンドで "マイティ・クィン"(ディランの曲)で日本でも知られたマンフレッド・マンのリード・ヴォーカリスト、ポール・ジョーンズが主演した映画『傷だらけのアイドル(Previlage)』の中で歌われた挿入歌。昔、この映画のサウンドトラックLPを持っていたのですが、手放してしまっていました。ところが2020年に突然、主題歌と挿入歌のヴォーカル曲全3曲をフィーチャーした米編集盤の復刻CDが日本で発売されました。`60年代の曲らしく3分未満の短い曲ですが、若干ソウルっぽい部分もありとても印象深く耳に残っています。  |
|||
| Title | Original Singer or Group | Cover Singer or Group | Song Writer |
| Get Ready | Rare Earth (1969's Album "Get Ready" & 1970's Single) | Smokey Robinson | |
1970年にシングル化されアメリカで大ヒットした曲ですが、最初に出たのは`69年同タイトルのアルバム収録曲で21分を超える曲。シングル化された時は3分以内に短縮されて発売されました。作曲はモータウンのミラクルズで活躍しソロ・シンガーとしても有名なR&Bシンガー、スモーキー・ロビンソン。日本では最初のディスコ・ブーム時にヒットしたのでシングル盤よりアルバムの方が売れたと思います。ディスコで人気だった曲なのでR&B・ソウル系の曲乍らもドラムスやベースの音は完全にロックで、レア・アース自体もロック・バンド (ファンク・ロック分野) としての認知が通常です。一度聴いたら忘れられない曲です。 |
|||
| Title | Original Singer or Group | Cover Singer or Group | Song Writer |
| I Have't Got the Nerve (内気な恋心) | The Left Banke (1966's Single & 1967's Album "Walk Away Renée/Pretty Ballerina") | George Cameron, Steve Martin-Caro | |
レフトバンクの "いとしのルね Walk Away Renée" はBB誌で5位迄上がるヒットと成り日本でもそこそこのヒットをし名前は早くから認知されていたと思いますが、長続きはせず懐かしのバンドと成っていった様です。 プロコル・ハルムの "青い影 A Whiter Shade Of Pale" に続く様なクラシック風味を持ったポップスでした。ただ、その "いとしのルネ" のB面に収録されたこの曲はポップ調でなくロック。ナンバーです。`60年代ガレージ・バンドの雰囲気を味わえる懐かしのロック・ナンバーで良い感じです。 このレフト・バンクの次のシングルもA面は "夢見るバレリーナ" という青春ポップスですがB面は "レイジー・デイ" というロック調の曲です。レコード会社の販売方針だったのかも知れませんが、ロック部分を押し出せばもう少し知名度が上がっていたのかも?とふと思いました。 |
|||
| Title | Original Singer or Group | Cover Singer or Group | Song Writer |
| Tell Her No (テル・ハー・ノー) | The Zombies (1964's US Album "The Zombies" & Single) | Juice Newton (1983's Single) | Rod Agent |
ゾンビーズは "Time of the Seasons ふたりのシーズン" についで2曲目に成ります。わたしの持っているのはベスト物アルバム収録ですが、初出は "She's Not There" のヒットを受けて米盤編集のファースト・アルバムに収録されて紹介(本国英盤ファーストには未収録)。そしてシングル化もアメリカの方が早く`64年12月で本国では約ひと月遅れの`65年1月での発売に成っていた様です。ゾンビーズの曲は概ねイギリスよりもアメリカでの方がヒットの確率は高くこの曲も全米6位迄上がっています。確かに‘60年代前半のアメリカンポップスの雰囲気を持ったロック・ナンバーで、イギリスのこの時期はもう少しブルーな曲調が求められ始めの頃だったのでしょう。 |
|||
| Title | Original Singer or Group | Cover Singer or Group | Song Writer |
| Tabacco Road | John D. Loudermilk (1960's Single) | The Nashville Teens (1964's Single & Album) Rare Earth (1969's Album)) Eric Burdon & War (1970's Single) & Others |
John Dee Loudermilk |
この曲 "タバコ・ロード" は英ブルース・ロックを聴きこんでいたいた時期にナッシュヴィル・ティーンズで知った曲です。ナッシュヴィル・ティーンズの代表曲でありセッション・ミュージシャン時代のジミー・ペイジが参加していた曲ということも有り結構ファンの間では人気のある曲でした。ただ、彼らのオリジナルでなくオリジナルはジョン・ディー・ラウダーミルクという白人歌手でカントリー系の曲を書いていた売れないシンガーだということで、ブルースっぽさはない人の作品でした。永らくオリジナルは聴けませんでしたが、ロカビリー系の発掘が盛んなドイツのBear Family がCD化して入手できました。エディ・コクランの "バルコニーに座って" などのオリジナル・ロカビリー曲と一緒に入っていました。オリジナルは確かにカントリー系のスロー・ロカビリーでした。ナッシュヴィル・ティーンズがブルース系にアレンジしていたのでした。レア・アースは Motown のバンドらしく黒っぽいフィーリングでブルース風です。 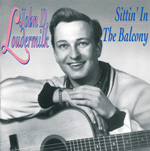 ※最初、`70年代以降のロックページで記載していた物。記載ページの間違いに気づきこちらへ移しました。 |
|||
| Title | Original Singer or Group | Cover Singer or Group | Song Writer |
| TNT | The Nashville Teens (1964's Single) | John Hawken | |
ナッシュヴィル・ティーンズという名前は、アメリカの若者が組んだカントリー系バンドでだと思っても不思議ではないバンド名ですが、実際はイギリスのウェーブリッジ 地区で結成されたビート・バンドでした。 "Tobacco Road" という英米での大ヒット曲を持ちながらもその後は尻すぼみで、バンド名だけが有名でヒット曲を日本では殆んど知られていないバンドです。ビートルズやR・ストーンズなどがオリジナル曲を連発したのと対照的に、殆どがカヴァー・曲ばかりの録音で有ったのが、実力を披露できなかった要因なのかもしれません。ジョン・ディー・ラウダーミルクの曲をいくつかカヴァーしているのからも判る様にカントリー系が好きでバンド名を付けた感じですが、ウィリー・ディクスンやボ・ディドリーの曲のカヴァーもしているのでブルースやR&Rの要素も結構持ったバンドでした。この曲 "TNT" は数少ないメンバーのオリジナル曲で、ほぼ完璧なブルース・ロックで当時の英国ブルース・ロックブームの先駆けの様な感じです。ただ、シングル発売時はジョン・ディー・ラウダーミルクのカヴァー曲 "Google Eye" の裏面でした。 |
|||
| Title | Original Singer or Group | Cover Singer or Group | Song Writer |
| The Legend of Xanadu (キサナドゥーの伝説) | Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich (1968's Single & Album "If No-One Sang") | Ken Howard、Alan Blaikley | |
イギリスのポップス系バンドで、「デイブ・ディー、ドジー、ビーキー、ミック&ティック」という原名の訳語名で一度紹介されながら、その英語名が長いため「デイヴ・ディー・グループ」という省略名で再紹介されてヒットを出す様に成ったグループ。結構多くのヒット曲を出していますが、殆どがイギリス、アイルランド、ドイツなど欧州でのことでアメリカでは何故かヒットを出せなかったバンドです。 この "The Legend of Xanadu キサナドゥーの伝説" は欧州圏で1位〜5位に成る大ヒットは勿論、アジア圏でもヒット、日本でも大ヒットし、グループ・サウンズのジャガーズの日本語ヴァージョン (キサナドーの伝説と少し変えていました) も共にヒットしています。確かにロック調ナンバーながら東洋人が好みそうなメロディーが印象的で「〜の伝説」と付けた邦題も good でした。 |
|||
| Title | Original Singer or Group | Cover Singer or Group | Song Writer |
| My Lonely Sad Eyes | Them (1966's Album "Again") | Maria Mcckee (1993;s Album) | Van Morrison |
"Gloria" や "Here Comes the Night" のヒットを放ったゼム。初期にヴァン・モリソンが率いていた事で有名なブリティッシュ・グループ(イギリス領の北アイルランド出身)の曲であり乍らあまり知られていない曲。 わたしもLP時代に米盤編集のファースト・アルバムと 『Backtrackin'』というコンピレーション盤を持っていましたが、そこには収録されていませんでした。その後バブル崩壊寸前に出たベスト盤『Them Featuring Van Morrison』で知った曲です。黒っぽいサウンドを主にしていたゼムですが、`70年代にブームに成ったジャクソン・ブラウンやリンダ・ロンシュタット、イーグルスなどに通ずるウエスト・コースト・サウンドを思い起こさせるアメリカンぽいサウンドが妙に新鮮で気に入りました。 |
|||
| Title | Original Singer or Group | Cover Singer or Group | Song Writer |
| Here Comes the Night (ヒア・カムズ・ザ・ナイト) | Lulu (1964's Single & Album "Something To Shout About" CD Version) | Them (1965's Single) David Bowie (1973's Album) |
Bertrand Russell Berns |
上記ゼムが放った最大ヒットは "Here Comes the Night" (全英2位、全米24位) ですが、ずっと彼らが最初の録音アーティストなのだと思っていました。でも調べてみると、実際はルルが半年ほど前に発表していた曲だったのです。 確認すればゼムのオリジナル曲でもなく、作者は`60年代に多くのヒット曲 (ツイスト&シャウト、渚のボードウォーク、テル・ヒム、エブリバディ・ニーズ・サムバディ・トゥ・ラブ 等) を放っているソング・ライター、バート・バーンズ (バートランズ・バーンズ) でした。オリジナル曲を持たないで活躍している人に提供するのはまず納得です。 わたしは英国女性シンガーのルルやダスティー・スプリングフィールドなどポップス系〜ソウル系を歌う人たちも好きでアルバムも結構持っています。ただ彼女たちは他人のヒット曲を自身の歌唱力で表現して歌うことが多いので、最初に楽曲提供を受けることは発表作の2割〜3割程度だとの思いでした。 ルルのヴァージョンはイギリスで50位のヒットだった様で、ソフト・ソウルタッチのアレンジ。ゼムの方はかなり粘り気のあるR&Bタッチのロックで`60年代バンドのブームにハマった見事なアレンジだったと感じます。 デビッド・ボウイも『Pin Ups』でカヴァーしていますが、こちらもボウイ節がハッキリと聴きとれる味のあるヴァージョンです。元のメロが良いのでしょうね。 |
|||
| Title | Original Singer or Group | Cover Singer or Group | Song Writer |
| Here We Go 'Round The Mulberry Bush (茂みの中の欲望) | Traffic (1967's Single & `68's Sound Track Album "Here We Go 'Round The Mulberry Bush") | Chris Wood, Dave Mason, Jim Capaldi, Steve Winwood |
|
スティーヴ・ウィンウッドは`63年のスペンサー・ディヴィス・グループからトラフィック、ブラインド・フェイスといったロック界の重要なバンドを渡り歩いてその後は実力派ソロ・シンガーとして今なお活躍している人ですが、参加バンドにはそれほどの思い入れも無くそれぞれのアルバムは数枚ずつの所有に留まっている範囲です。 S・ウィンウッドはどちらかというとR&B系のヴォーカルを得意としているヴォーカリストですが、この曲はコメディー映画音楽用として作られている為か、かなり明るいポップ調の60年代ロックです。トラフィック・ナンバーの中では一番好きな曲です。 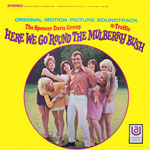 |
|||
| Title | Original Singer or Group | Cover Singer or Group | Song Writer |
| All Day and All of the Night (オール・オブ・ザ・ナイト) | Kinks (1964's Single) | Ray Davies | |
キンクスも、リーダーだったレイ・ディヴィスの才能によってブリティッシュ・ロック界では重要なグループとして認知されています。世間ではハード・ロックへの影響が強いと言われていますが、わたしが感じるのはどちらかというとヘヴィー・ロックといわれるジャンルに影響を及ぼしたのでは?と思います。 後のステッペンウルフ、ドアーズ、グランド・ファンク・レイルロード、バックマン・ターナー・オーヴァードライヴ など。主に北米ロック・バンドの音楽と似ていそうです。 "You Really Got Me " で全英No.1、全米5位のヒットを放ち、次いで出たシングルがこの曲でこちらも全英1位、全米6位と (次作 "Tired of Waiting for You" も同様ヒット) ほぼ両国のヒットチャートを数週間賑わしていた感じです。 この連続大ヒットの三曲の中でこの曲が一番好きです。この曲の最も印象的なサビの部分が約3年半ほど後に出たドアーズの "Hello, I Love You" のテーマ部分がそっくりで、「ぬけぬけ、堂々と」といった感じでしたが盗作問題には成らなかった様です。レイ・ディヴィスの心の広さ! |
|||
| Title | Original Singer or Group | Cover Singer or Group | Song Writer |
| Victoria (ヴィクトリア) | Kinks (1969's Single) | Ray Davies | |
キンクスは`64年から`65年中頃までとそれ以降で全く違うバンドの様に思える程変化を遂げて行っていると思えます。`66年頃から`67年頃はどこかドラマティックな要素を含んだ音作りで、後の`70年代に出現したデヴィッド・ボウイを思い起こさせる作風の曲を作っていたのです("Dedicated Follower Of Fashion" などボウイの曲かと思えるほどです)。そしてこの曲 "Victolia" はほぼ正反対の曲調でイギリス風からアメリカ風に海を渡った感じです。このリズムの使い方はアメリカらしさ満載のドゥービー・ブラザーズ (初期トム・ジョンストン主体の頃第一作から『Stampede』頃迄`) がよく使っていたリズムです。勿論キンクスの方が先なのですが. . . この曲発表は1969年12月と`60年代ロックギリギリです。レイ・ディヴィスという人、ホントに才能ある人なのですね。曲作りが変化して行っているのもデヴィッド・ボウイ風です。 |
|||
| Title | Original Singer or Group | Cover Singer or Group | Song Writer |
| I Had Too Much To Dream (Last Night) (今夜は眠れない) | THe Electric Prunes(1966's Single & `97's First Album") | Annette Tucker, Nancie Mantz | |
「驚きの電撃的なサウンド」「エレクトリックサウンドの先駆者」とオールド・ロック界では名前だけは知れ渡っていたエレクトリック・プルーンズ。サイケデリック・ロックバンドの一組として登場してきた時期にラジオで何度も聴いたことがありましたが、LPを買ったのは`80年代初めでしたので、既にハード・ロック全盛時。特に目新しいサウンドではなく成っていました。このファズを使った荒々しい音作りはデイヴィッド・ハッシンジャーというR・ストーンズのサウンド・エンジニアがプロデュースした事に依ると言われているらしいです。全米11位のヒットでしたが、確かに`60年代ロックを振り返る際には外せない一曲なのでしょう。 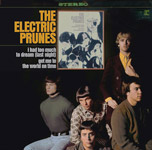 |
|||
| Title | Original Singer or Group | Cover Singer or Group | Song Writer |
| With a Girl Like You (ウィズ・ア・ガール・ライク・ユー) | Troggs (1966's Single as B-side "Wild Thing") | Reg Presley | |
英国ビート・グループのトロッグスは`66年に「恋はワイルド・シング "Wild Thing"」を全米1位、全英2位に成るヒットを出して一躍名前を知られる様に成っていますが、日本では余程のマニアでもない限りその一曲でしか知られていないと思える程のビートバンドといった感じです。この曲 "With a Girl Like You" は最初米 Atco レーベルから "Wild Thing" のB面として発売された後二か月程して英 Fontana からA面にして発売された模様。そしてイギリスでのヒット・チャートで1位に成るヒット成っています(米BB誌では29位)。 "Wild Thiing" は "Angel of the Morning" の作者、チップ・テイラーながらこの曲はメンバーのヴォーカリスト、レグ・プレスリー作曲で、"Wild Thiing" で感じた独特の粘っこいヴォーカルは控えめでポップさを持った楽しい感じの曲です。個人的には断然こちらの方が好きです。 |
|||
| Title | Original Singer or Group | Cover Singer or Group | Song Writer |
| I Can't Control Myself (ボクは危機一髪) | Troggs (1966's Single) | Reg Presley | |
"With a Girl Like You" の次に英 Fontana から出たシングルで、この曲もレイ・プレスリーの作曲。イギリスで2位迄上がるヒットと成っています。前作よりはロックっぽさは増していますが、聴き返すとやはり`60年代らしさを感じます…がそこがまたオールド・ロック大好き派には嬉しいところです。 この「危機一髪」という何故か時代を感じる邦題と相まって記憶に留まる一曲です。 |
|||
| Title | Original Singer or Group | Cover Singer or Group | Song Writer |
| I Can Hear The Grass Grow (みどりの草原) | The Move (1967's Single) | Blues Magoos (1968's Album) Status Quo (1996's Album) |
Roy Wood |
ザ・ムーヴは1960年代後半にブリティッシュ・ビートバンドが乱立していた頃のバンドのひとつで、音楽的には黒っぽかったキンクスやスペンサー・デイヴィス・グループとは違いかなりポップ調の曲が主体でした。日本での人気はキンクスやS・D・グループにほどには上がらなかった様です。ただ、創立メンバーのひとりロイ・ウッドやその後の後期に加入するジェフ・リンと後に組んだエレクトリック・ライト・オーケストラの知名度によって再認識されたバンドです。 この曲はポップ系の中でも割とロックっぽい出来の曲で英国ヒットチャート5位迄上がっています。 |
|||
| Title | Original Singer or Group | Cover Singer or Group | Song Writer |
| Murder In My Heart For The Judge | Moby Grape (1968's Album "Wow") | Don Stevenson, Jerry Miller | |
この頃はひと月に一枚のシングル盤(若しくは4曲入りコンパクトLP)をお小遣いで買う程度でした。多くの曲はラジオで聴いて過ごしていた時代でその時聴いた多くの曲は今でも忘れる事の無い曲ばかりです。 その様な中でこのモビー・グレイプの曲は本国アメリカでも殆んどヒットしなかった様で日本のラジオで流れることは極端に少なかったと思います(わたし自身は聴いた記憶にないです)。それでも名前だけは知っていました。当時の音楽情報誌『Music Life』の記事の中、フラワー・ミュージック、サイケデリック・ロックバンドの紹介中に名前が有ったのです。そして多くの音盤を買える時代に成ってから漸く手元で聴くようになりました。 この曲を聴いた最初の印象は`70年初頭にアメリカン・ミュージックの先端に位置していた [アル・クーパー] を 思い浮かべたのです。多くのジャンルを組み入れて融合させていた当時では新しいロックを作ろうとしていたアル・クーパーです。そのアル・クーパー自身もこのアルバムから影響を受けたと言っていた様です。 |
|||
| Title | Original Singer or Group | Cover Singer or Group | Song Writer |
| Can't Be So Bad | Moby Grape (1968's Album "Wow") | Don Stevenson, Jerry Miller | |
もう一曲、モビー・グレイプですが、BB誌で80位台のヒットと成った "Omaha" やこの様なタイプの曲が有るので日本ではサイケデリック・ロックバンドの一組として紹介されていたのでは?と思います。モビー・グレイプはもともとフォーク系志向だった若者たちが結成したバンドとかで、ボブ・デイランタイプのフォーク調も含めて結構多様なジャンルの曲調の曲を演奏しています。 この "Can't Be Sp Bad" は英国ビート・バンド風な曲調ですがギター・エフェクトの使い方などがこの時代のわたしが思うサイケデリック・ロックを感じさせる演奏です。チャートインした "Omaha" よりこちらの方が昔言葉で云うと断然「カッコイイ」ロックです。 人によってはピンク・フロイドやビートルズの "Strawberry Fields Forever" なども幻想的でサイケデリック・サウンドだと言われておられます。ことば自体は懐かしい言葉ですが2〜3年で使われなくなったジャンルでした。 |
|||
| Title | Original Singer or Group | Cover Singer or Group | Song Writer |
| Feel It for Me | Ten Years After (1967's Album "Ten Years After") | Alvin Lee | |
上の方で "I Woke Up This Morning (夜明けのない朝)" を取り上げていましたが、もう一曲テン・イヤーズ・アフターを、ファースト・アルバムから "Feel It for Me"。シカゴ・ブルースからの影響をモロに感じますが、クラプトンや、ベック、ペイジなども同じ時代にシカゴ・ブルースの影響を受けて世界へ飛び出していったという事を思うと、`60年代の英国ミュージシャン達はホントに凄かったのです。 こういった熱い演奏をいつでも繰り返して聴き続けたいものです。このアルバム内では他人の曲を半数位凄い演奏で収められていますが、アルヴィンの作曲能力も結構なものでオリジナルからの一曲。 |
|||
| Title | Original Singer or Group | Cover Singer or Group | Song Writer |
| I Smell Trouble | Savoy Brown Blues Band (1967's Album "Shake Down") | Deadric Malone(= Don Robey) | |
ブリティッシュ・ブルース創成期、ピーター・グリーン在籍時のフリートウッド・マックを聴き込んでいた時期にサヴォイ・ブラウンの妙ちくりんな写真付きのメガネをかけたカバーデザインのアルバムを輸入盤店で何度か見かけて気には成っていました(それはサヴォイ・ブラウンのセカンド・アルバムでした)。ただ、私が先に買ったのはこの実質ファーストの方でバンド名義が Savoy Brown Blues Band と成っていた方です。メンバーはリーダーでギターリストのキム・シモンズ以外は入れ替わっていますが、キムのブルース・ギターは絶品です。ジョン・メイオールのバンド出身では無かったのでそこまで名は売れなかった様ですが、長くに渡りブルース・ロックを追及してきたブルースひと筋のギターマンです。 このファーストだけ、ヴォーカルが黒人の Brice Portius という人で、セカンド以降のヴォーカリストたちと比べると、さすが乍らブルース色が強い凄いヴォーカルだと感じました。 |
|||
| Title | Original Singer or Group | Cover Singer or Group | Song Writer |
| Hey Baby Everything's Gonna Be Alright Yeh Yeh Yeh (ベイビー、気ままに行こうぜ) | The Climax Blues Band (1969's Album "Plays On.") | Climax Blues Band | |
イギリスのブルース・ロック・ブームの中で生れたバンドでこのクライマックス・ブルース・バンド(最初はクライマックス・シカゴ・ブルース・バンド名)も、忘れられないバンドです。 このバンドは結成時の名前に「シカゴ・ブルース」という単語が付いている位ですからモロのシカゴ・ブルース演奏バンドだったのです。`70年代以降は徐々に変化して行っていますが、この`69年のセカンド・アルバムではほゞエレクトリック・ブルース、シカゴ・ブルースです。HR/HM系を聴いたり、ソウル・ミュージックを聴いたりしていても、こうした時代を感じるブルース・ロックを時には聴きたくなるのは、聴いて育った昔があったからでしょう。 作者はメンバ=全員、作者名クレジットには「The」の冠詞が付いていませんがバンドの正式名でも1970年以降は冠詞を取っての表記が使われている様です。 |
|||
| Title | Original Singer or Group | Cover Singer or Group | Song Writer |
| Michael's Lament (マイケルの嘆き) | Michael Bloomfield (1969's Album "It's Not Killing Me") | Mike Bloomfield | |
生まれがシカゴで幼いころからシカゴ・ブルースに縁が有ったと言われたアメリカンブルース・ロック・ギターリストのマイク・ブルームフィールド。彼の参加したバンドのバターフィールド・ブルース・バンド (このページ上の方) 、KGB (70年代ロックページ) にエレクトリック・フラッグ (上の方、ハウリング・ウルフのカヴァー) 等といろいろなバンドでギターを披露しており、好きなギターリストひとり、マイクのソロ・アルバムからの一曲。(名義はMichael Bloomfieldで) スロー・ブルース、泣きのブルースですが、どちらかというとシカゴ・ブルース系より南部のカントリー・ブルースっぽい感じです。ギターリストとして有名ですが、この熱のこもったヴォーカルも捨てがたく聴き物です。 |
|||
| Title | Original Singer or Group | Cover Singer or Group | Song Writer |
| Can't Keep From Cryin' Sometimes (キャント・キープ・フロム・クライン) | AL Kooper 1966's Album "What's Shakin'") | The Blues Project (1966's Album) Ten Years After (1967's Album) |
Al Kooper (alteration, adaption) |
この曲の収録は1966年に英Elektraレーベルから出た3バンドと2シンガーによる編集盤『What's Shakin'』に収録された曲で、アルバム自体が後にエリック・クラプトン、ポール・バターフィールド・ブルース・バンドなど参加の為にブルースロックファンの間で有名になった盤です。そしてこの曲は結構いわく付きの曲で、作者はアル・クーパーとクレジットされていましたが、後にブルース・シンガー、ブラインド・ウィリー・ジョンの`29年発表 "Lord I Just Can't Keep From Crying" の改変作だという話になり、近年この曲の作者欄には「ウィリー・ジョンソンの名は出さずに、アル・クーパー(アレンジ)」といった形で表示されることが通常の様です。少々の変更ならアレンジでしょうが大幅に変わっていたら改作表示の方では?とも思いますが。 『What's Shakin'』収録時点の邦題は「キャント・キープ・フロム・クライン」でしたが、後にブルース・プロジェクトやテン・イヤーズ・アフター再演奏発売の後は原題は "I Can't Keep From Crying Sometimes" に、邦題は「泣かずにいられない」とか「泣きたい心」等の邦題に替えられその後定着しています。 このアルバム内での演奏はロック・タイプに成っていますが、ブルース・プロジェクトでアル・クーパーが再演した時はヴォーカルがスティーヴ・カッツに成っていて、より確実なロック・ナンバーに、そしてテン・イヤーズ・アフターヴァージンでは、アルヴィン・リーのギターがブルース色を高めて聴き応えのあるブルース・ロックナンバーに成っています。聴くならやはり Ten Years After ヴァージョンです。 ちなみにジョージ・ハリスンの曲 "This Guitar (Can't Keep From Crying)" というのがあり、そちらの邦題は「ギターは泣いている」です。 |
|||
| Title | Original Singer or Group | Cover Singer or Group | Song Writer |
| Fire | The Jimi Hendrix Experience (1967's Album "Are You Experienced") | Jimi Hendrix | |
`60年代で忘れてはならないギターリスト。ジミ・ヘンドリックスは "Purple Haze 紫のけむり"、"Foxy Lady フォクシー・レディ" などは日本でもヒットしていてラジオで頻繁に流れていました。数年たってジミのアルバムを最初に買ったのはセカンド・アルバムで、割とがっかりした気分だったと記憶しています。その後やっとその2曲が入った米盤のファースト・アルバムを買ったのです。(日本盤には" 紫のけむり"が入っていなかった)、その中でその2曲よりも気に入ったのがこの "Fire ファイアー" でした。三人のコラボ(特にドラムスが良い)演奏が曲の良さと絡み合ってアルバム中一番のロック・ナンバーだと感じました。  |
|||
| Title | Original Singer or Group | Cover Singer or Group | Song Writer |
| Voodoo Chile | The Jimi Hendrix Experience (1968's Album "Electric Ladyland" & 1970's Single) | Jimi Hendrix | |
ジミ・ヘンドリックスの演奏の中でこの "Voodoo Chlile" が一番好きです。15分近くの演奏ですが完全に入り込めるのめり込めるブルース・ロックです。ジョン・コルトレーンの "Live at the Village Vanguard" A面もも14分ほどサックスを吹きまくりの演奏で、ジャズ喫茶でのめり込んで聴いていましたが、この曲も同じように人を引き寄せる力を持っていると思います。またこのアルバムにはデイランのカヴァー "All Along the Watchtower" の絶品も入っておりジミヘンの中でも好きなアルバムでもあります。編集物アルバムの中に『Blies』というジミヘンのブルース演奏集がありますが、あのアルバムも大好きです。 |
|||
| Title | Original Singer or Group | Cover Singer or Group | Song Writer |
| Summer in th City | The Lovin' Spoonful (1966's Single & Album "Hums of the Lovin' Spoonful") | John Sebastian, Mark Sebastian, Steve Boone | |
ラヴィン・スプーンフルは、上の方で記した曲、 "Can't Keep From Cryin' Sometimes" の初収録アルバム『What's Shakin'』内で最もフィーチャーされたバンドでオムニバス系作品なのにカバー写真も彼らで、バンド名も (まるで自身バンドのアルバムの如くに) 大きく表示されていました。 本来はフォーク・ロック系のバンドで、ボヴ・デイランがロック化した頃から広がったジャンルかと思います。"Did You Ever Have to Make Up Your Mind?"、"Do You Believe in Magic" 等のヒット曲はフォーク・ロックの代表曲として今も残っていますが、この "Summer in the City" だけは別格にロック色が強くハード・ロックの生前前の趣がします。まず一度聴いたら忘れられないインパクトを持っています。 |
|||
| Title | Original Singer or Group | Cover Singer or Group | Song Writer |
| No Time | The Guess Who (1969's Album "Canned Wheat" & Single) | Randy Bachman, Burton Cummings | |
| ゲス・フーは上の方で "These Eyes" を取り上げていますが、この曲は当時流行っていたサイケデリック・サウンドと呼ばれるような幻想的なサウンドを取り入れた曲なので、その時代の音楽を聴いていた者には明らかに時代を感じる部分はありますが、だからと言って古さを感じることはありません。不思議な魅力を持っている曲だと思います。ゲス・フー自体はいろいろなタイプの演奏が出来作る実力を持ったバンドです。この曲はアルバム・ヴァージョンで選んでいますが、シングル化時は前半部分などをカットした短めで出されました。シングル・ヴァージョンは次のアルバムに収録されています。シングル盤はBB誌HOT100で5位のヒットと成り本国カナダでは1位ヒットです。この曲の作者ランディ・バックマンとバートン・カミングスは後のロック界でもB.T.O.など個々に活躍を続けている重鎮ミュージシャンです。 |
|||
| Title | Original Singer or Group | Cover Singer or Group | Song Writer |
| Touch 'Em with Love | Bobbie Gentry (1969's Album "Touch 'Em with Love" ) | John Hurley, Ronnie Wilkins | |
| ボビー・ジェントリーと云うシンガー、『ビリー・ジョーの唄』、アメリカで大ヒットしていた時期は日本のラジオでもしょっちゅう流れていました、飽きる程でした。彼女の自作曲で短かく同じフレーズが淡々と流れる曲ながら覚えきってしまう程不思議な曲でした。そのおかげだったのかどうかレコードを買ったのはヒットから10年近く経ってからでした。 日本ではいわゆる「一発屋」と呼ばれるシンガーに入るのかも知れませんが、本国ではその後も中ヒット、小ヒットをいくつも出しておられます。『ビリー・ジョーの唄』は自作でしたがこの曲は ジョン・ハーレーとロニー・ウィルキンスというソングライター・コンビの曲でロック調です。 |
|||
| Title | Original Singer or Group | Cover Singer or Group | Song Writer |
| I Wanna Be There | Blues Magoos (1967;s Single & 1968's Album "Basic Blues Magoos") | Emil Thielhelm, Ralph Scala | |
| ブルース・マグースはページ内のかなり上の方でBB誌チャート5位迄上がり日本でもヒットした "(We Ain't Got) Nothin' Yet 恋する青春" を取り上げていましたが、この曲 "I Wanna Be There アイ・ワンナ・ビー・ゼア" は。BB誌チャート133位と「HOT100」内に入れない程度のヒットでした。`60年代後半という時期は洋楽をラジオにかじりついて聴いていた時期で、殆どのヒット曲を覚えていますが、確かにこの曲がラジオで聴いた記憶はわたしには残っていまませんでした。三枚目のアルバムに収録され、その後に聴いたのですがアルバム内では一番ロック調でヒット性のある曲ではありました。新しいグループが次々と出ていた時代でしたので埋もれて仕舞ったのでしょうね。 |
|||
| Title | Original Singer or Group | Cover Singer or Group | Song Writer |
| Kansas City Sourthern | Dillard & Clark (1969's Album "Through The Morning Through The Night") | Gene Clark | |
`60年代発売の曲ですが、わたしがこの曲収録のアルバムを買ったのはグラム・パーソンズを中心としたカントリー・ロック系を良く聴いていた`70年代後期で (多分日本発売初だと思うのですが) 邦盤としてのタイトルが『朝の光の中で』として出された盤で`78年に購入しています。ジーン・クラークは元バーズですが、サポート・メンバーが気に成る存在。同じく元バーズ・メンバーでグラム・パーソンズと一緒にフライング・ブリトー・ブラザーズを結成したクリス・ヒルマン、そしてF.Bブラザース参加の後、創設期のイーグルスに参加したバーニー・レドンといった面々です。 ジーン・クラークはカントリー寄りの曲を書くときは良いのですが、ブルーグラス寄りに偏ると特徴が無くなりがちです。この曲はタイトルもヨシヨシのカントリー・ロックです。C.C.R. が奏りそうな曲ですね。 |
|||
| Title | Original Singer or Group | Cover Singer or Group | Song Writer |
| Bedsitter Images | Al Stewart (1967's Album "Bedsitter Images" & Single) | Al Stewart | |
| アル・スチュアートの曲は「ジャンル不問のページ」で "Carol" を取り上げていますが、あの曲は彼の曲の中で一番好きな曲です。彼の事を知ったのは`78年に邦盤発売された『Orange』なのですが、そのアルバムを気に入り遡って種々購入しました、その中でファースト・アルバム、トップに収められていたのがこの曲、 バックは室内楽合奏団の模様でフォーク調ながらかなりヨーロッパを感じる印象深い曲です。 |
|||
| Title | Original Singer or Group | Cover Singer or Group | Song Writer |
| Plenty Hard Luck | Colosseum (1969's Album "Those Who Are About to Die Salute You") | Dave Greenslade, Dick Heckstall-Smith, Jon Hiseman, James Litherland, Tony Reeves | |
コロシアムの曲も「ジャンル不問のページ」で "Elegy" を取上げていましたが、その曲の入ったアルバム "Valentyne Suite" (2nd) は‘73年に中古で入手したのですが衝撃的でした。当時ハマり込んでいたユーライア・ヒープを聴いた時と同じ位に衝撃的でした。この2バンドはヘヴィー・メタル以前のヘヴィー・ロックへと導いてくれたバンドです。 "Plenty Hard Luck" はそのコロシアムのファースト・アルバム収録曲。基本はブルース・ロックなのでしょうが、後にジャズ・ロック・バンドの代名詞になった様に、ジャズ的なサックスのソロを入れ込んで、聴き応え充分の一曲です。 |
|||
| Title | Original Singer or Group | Cover Singer or Group | Song Writer |
| Time of the Season (ふたりのシーズン) | The Zombies (1968's Single & Album "Odessey and Oracle") | Rod Argent | |
イギリスで`64年に "She's Not There" をヒットさせ、その後アメリカでもBB誌2位、CB誌1位に成るヒットを放ち一躍人気バンドに成ったゾンビース。直ぐに人気は尻すぼみ、`68年に解散してしまったのですが、アメリカでシングルカットされたこの曲が大ヒット(BB誌3位、CB誌1位)、日本でもかなりのヒットと成りました。ロッド・アージェントの最高傑作だと思えます。素晴らしい曲です。 |
|||
| Title | Original Singer or Group | Cover Singer or Group | Song Writer |
| I Love You | The Zombies (1965's Single) | The Carnabeats (1967's Single) |
Chris White |
この曲はオリジナルはゾンビーズなのですが、日本では日本語の歌詞が付けられてGSグループのカーナビーツが`67年にヒットさせ、そちらの方が大ヒット、曲名は「好きさ好きさ好きさ」として漣健児さんが詞を担当していました。ゾンビーズの方はイギリスやアメリカでもシングル化されていましたがヒットしませんでしたが、日本の担当者が見つけた曲なのでしょうね。`60年代のオールディーズ曲には本国でヒットしなかった曲が日本でヒットする事多々ありました。 「おまえのすべてぇ〜を」とドラムスティックを掲げるところがお決まりでした。 |
|||
| Title | Original Singer or Group | Cover Singer or Group | Song Writer |
| Geraldine | Boots Walker (1967's Single) | Lou Zerato | |
1969年に日本盤が発売され大ヒットしていましたが、本国アメリカでは`67年に発売されるも全くヒットしなかった曲です。Lou Zeratという作者とBoots Walkerは同一人物でどちらの名前でもレコード発売はされていた様ですが (ルー名義ではAtlantic,ブーツ名義ではRustやLaurieから) 殆どヒットしませんでした。ソングライターとしてはそこそこのヒット曲を書いていたらしいです。 この日本盤シングルに桜井ユタカさん、浅妻一郎さん、湯川れい子さん、星加ルミ子さんなど当時の洋楽雑誌執筆者たちが揃って推薦文を書かれているのが面白いです。 アメリカ発ながらどことなくヨーロッパの哀愁を感じる部分が日本で受けたのでしょう。  |
|||
| Title | Original Singer or Group | Cover Singer or Group | Song Writer |
| You Keep Me Hangin' On | The Supremes (1966's Single & 1967's Album "The Supremes Sing Holland-Dozier-Holland") | Vanilla Fudge (1967's Single)
The Ferris Wheel (1967's Album) The Box Tops (1968's Album) Kim Wilde (1986's Single) & Others |
Holland-Dozier-Holland (Lamont Dozier, Brian Holland, Eddie Holland) |
シュープリームス (スプリームス) の曲は[オールディーズポップス]ページで "恋はあせらず"、"ラブ・チャイルド" を取り上げていましたがこの曲も全米ヒットチャート1位の曲です。そして、カヴァーが多いことも有名でわたしも四種持っています。カヴァーしている殆どがロック・バンドであったりロック系シンガーであることから分かるように元歌のバック演奏は明らかにロック・アレンジです。(ということで ここ[60'sロック]ページで記します) バック演奏はモータウン・アーティストの多くで演奏しているファンク・ブラザース、そして作者はモータウンお抱えのソングライターチーム、ホーランド_ドジャー_ホーランド名義で活躍したトリオで、モータウン・レーベルで多くのヒット曲を作っていました。 カヴァーカヴァー群で最もヒットしたのがヴァニラ・ファッジの物でBB誌Hot100で8位まで上がり彼らのファースト・アルバムも売れて米アルバムチャートで6位です。日本でも「アート・ロック」というジャンルで話題を集めていました。ただ、個人的にはフェリスホイールやボックス・トップスの凝っていないヴァージョンの方が好きです。(ベックと組んだカーマイン・アピスやティム・ボガードの演奏は好きですが、このバンド自体が演奏していたロックには惹かれませんでした) |
|||
| Title | Original Singer or Group | Cover Singer or Group | Song Writer |
| I've Gotta Get a Message to You (獄中の手紙) | The Bee Gees (1968's Single & Album "Idea") | Barry Gibb, Robin Gibb, Maurice Gibb | |
ビージーズは`67年に「ニューヨーク炭鉱の悲劇」が最初にヒットして、日本でも知られるようになりましたが同時期大量にイギリスからのビート・バンドが出てきた中で、ロックビートを前面に出さない数少ないバンドでした。元々三兄弟のみでオーストラリアでヴォーカル・グループとしてレコードデビュー、その後イギリスへ戻り5人編成で再デビューしたという経緯からどちらかというとバンド形態サウンドというよりヴォーカル・グループに近いタイプです。 5人編成時の映像を見ましたが (おそらくエアー演奏ながら) コリン・ピーターソンがドラムスとして座っていますが、叩くような曲はほぼ無く撫でる様な曲が主です。よって「60年代ロック」のページで記す曲は無さそうでしたがこの曲は一応スロー・ロック・タイプです。それでもやはりヴォーカルを聴かせる曲ではあります。 |
|||
| Title | Original Singer or Group | Cover Singer or Group | Song Writer |
| Sun City | John Fred (1966's Single & 1967's Album "34:40 Of John Fred And His Playboys") | Harold Cowart, Lynn Ourso, Ronnie Goodson | |
この曲を歌ったジョン・フレッドは"Judy in Disguise ジュディのごまかし"をヒットさせたプレイボーイ・バンドのリーダー。元々1960年からソロ・デビューしていたらしくこの曲は`66年発売シングル。この頃まではソロ名義と「John Fred and the Playboys」の名称でバンド形態名義での両方で活動していたみたいです。アルバムに収録した際はバンド名義でアルバムに収録されました。そして`67年には「John Fred & His Playboy Band」とバンドの名称を変えて、ポップ路線で"Judy in Disguise"の大ヒットを生んだのですが、彼はルイジアナ州のバトン・ルージュの生まれ、音楽活動は明らかに南部サウンドがベースに有ったようです。 この曲はブルース・ロックとも思えるほどに黒いフィーリングを持っていて1966年という発売年を思うと「凄い!」と驚きます。 |
|||
| Title | Original Singer or Group | Cover Singer or Group | Song Writer |
| And When I Die | Peter, Paul And Mary (1966's Album "Peter, Paul And Mary Album") | Blood, Sweat And Tears (1968's Album)
Laura Nyro(1967's Album) & Others |
Laura Nyro |
フォーク・グループのPP&Mが最初の録音者・発売者なのに「ロック」のページに?とも思いますが、最初に聴いて知ったのはBS&Tのヒット・アルバム『Blood, Sweat And Tears 血と汗と涙』の一曲としてでした。翌年BS&T・ヴァージョンはシングル発売されてBB誌HOT100の2位の大ヒット、アルバムと共に広く知れ渡りました。 オリジナル録音者のPP&M・ヴァージョンを入手したのはCD時代に入ってからのかなり後でしたが、結構ロック的な要素もありフォーク・ロック的ではありました。 作者は後にソロ歌手として人気を得たローラ・ニーロで自身のヴァージョンはデビュー・アルバムに収録されている様です。 |
|||
| Title | Original Singer or Group | Cover Singer or Group | Song Writer |
| Cry Like a Baby | The Box Tops (1968's Single & Album "Cry Like a Baby") | Betty Wrigh (1968's Album) Dorothy Moore (1973's Single) Petula Clark (1971's Album) & Others |
Dan Penn, Spooner Oldham |
ボックス・トップスは上の方で "The Letter"、"Soul Deep" と二曲を取り上げていますので三曲目に成ります。BB誌のチャートでは "あの娘のレター"(1位)に次いで2位まで上がった彼ら2番目のヒット曲に成り、これも印象的な曲です。 `67年〜`69年までの3年間で4枚のアルバムを発表。そこそこの売れっ子バンドでしたが、`70年代以降は尻すぼみに成って行きました。`90年代に再結成はされていますが、初期三年間に残した録音は色褪せる事なく21世紀に成っても再発し続けられています。米南部のサウンドに妙にピッタリ来るアレックス・チルトンのクセに成る微妙な声質に引き込まれていきます。シングル化されなかったアルバム内の曲もホント味があります。 |
|||
|
|